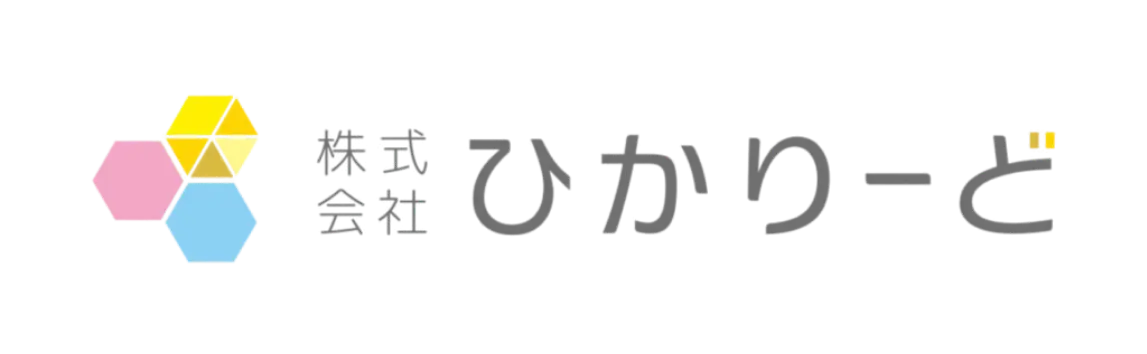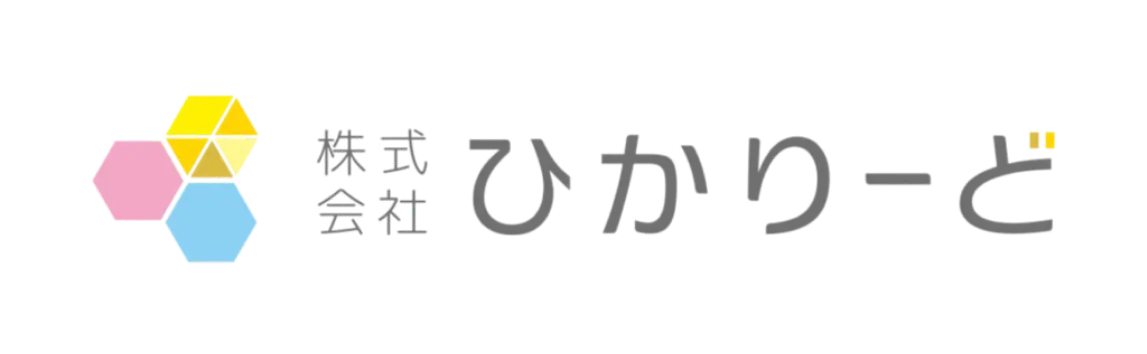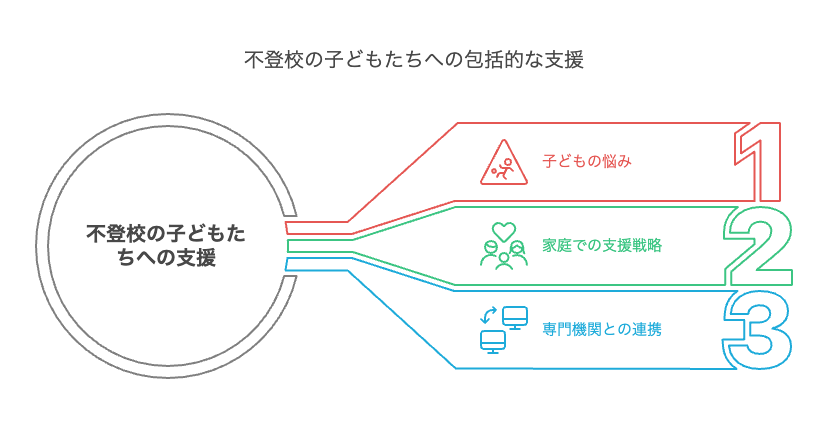
はじめに:不登校は誰にでも起こりうる
近年、不登校の子どもは増加傾向にあり、文部科学省の調査(令和4年度)によれば、小中学生の不登校児童生徒数は29万人を超えています。特別な事情がなくても、「なんとなく学校に行きたくない」という感覚から始まるケースもあり、不登校は“どの家庭にも起こりうる”問題です。
不登校の子どもが抱えている主な悩み
1. 学校での人間関係のストレス
いじめやグループ内での孤立、友人関係のすれ違いなどが大きな原因になることがあります。特に小学生〜中学生では、相手との距離感をうまく取れない子どもがトラブルに発展しやすく、学校に行くこと自体が恐怖になります。
2. 学習についていけない不安
授業が難しい、宿題が多すぎる、成績が伸び悩んでいる…。このような焦りや自己否定感は、不登校につながることがあります。特に発達特性がある子どもにとって、通常の学習環境は大きな負担になります。
3. 家庭とのコミュニケーション不足
家族に自分の悩みを伝えられない、親が忙しくて話を聞いてくれないなど、家庭内での「安心感」が失われていると、子どもは心を閉ざしてしまいます。
家庭でできる5つの支援法
1. 子どもの話を否定せずに聞く姿勢
まずは「聞くこと」が最優先。アドバイスよりも、「そう思ったんだね」と気持ちを受け止めることが信頼関係の第一歩になります。
2. 小さな成功体験を積ませる工夫
ゲームのクリア、料理の手伝いなど、学校以外でも「自分はできる」という感覚を育てることで、自信が芽生えてきます。
3. 生活リズムの見直しと習慣づけ
朝起きて朝日を浴びる、食事の時間を整えるなど、生活のリズムを安定させることは、心の安定にもつながります。
4. 安心できる居場所を家庭に作る
「学校に行かないことを責めない」「自分のペースで過ごせる空間をつくる」といった工夫で、子どもが安心できる“ホームベース”を育てましょう。
5. 専門機関や支援団体との連携
保健センターや教育支援センター、フリースクールなど外部の支援も積極的に活用することで、親自身の負担も軽減されます。
支援を続ける上で親が気をつけたいこと
「すぐに登校できるように」と焦らず、長期的な目で見守ることが大切です。また、親も1人で抱え込まず、専門家や同じ立場の親同士で気持ちを共有しましょう。
まとめ:一人で抱えず、周囲と協力しながら支援を
不登校は“家庭の失敗”ではありません。むしろ、子どもが自分の声を届けようとしている大切なサインです。温かく寄り添い、専門機関や支援団体と連携することで、子どもは少しずつ自信を取り戻していきます。
✅ 参考文献・統計
• 文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
• 辻井正次(2019)『発達障害の子どもを理解する』ミネルヴァ書房
• Ogino T, et al. (2020). Psychological characteristics of school-refusal children. Journal of Child Psychology.